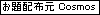■僕から見た君で50のお題■
11.血で染まった僕を見て君は後ずさった ※R12
「‥‥い‥ッ!」
苦鳴に篭った意味を自分に良いように捻じ曲げているのはわかっていた。
「ギギナッ!」
わかっていても、吐かれた音が己の名である以上は止まれなかった。
例えそれが拒絶でしかない絶叫でも、だ。
「ア、ぐ!」
細い首。筋ばったその根元に、誘われるままに歯を立てれば生暖かい血が流れる。
傷口に舌を這わせて舐め上げれば、細い死体が腕の中で慄いた。
常から赤い口唇を更に彩る朱を認めた蒼い瞳がぐらりと揺らぐ。
逃げようとした肩が背後を望むが、壁と布が擦れる音がしただけ。
二人の距離は変わらなかった。
12.君がいなくなった朝は僕はただ呆然として
一昨夜よりも狭くなった、昨夜続きの寝台の上。
半覚醒のまどろみの中で腕を彷徨わせるが、しかし白磁のそれは虚しく空を切るばかり。
求めた温もりを掴むことは無かった。
「‥‥」
ぱちり、と目だけは開いている。
しかし思考は纏まらず、短針が刻む規則的な時間だけが一秒一秒積もってゆく。
「、ガユスッ!?」
ただ呆然とするしかない時間に終わりを告げて、既に冷え切っていた寝台から飛び降り、寝室から外へと繋がる扉へと一足飛び。取っ手を手に掛け飛び出そうとしたが、急いた身体は特急く身体と連携が取れず、目算誤り閉じたままの扉へ身体を打ちつけた。
思わずその場に屈み込む。
「‥‥なにやってんの?」
己の力では開けなかった扉の向こう、不思議そうな目で私を見下ろす男。
その手に湯気を立てる陶杯が二つあるのを確認した途端、言われた通り素直に、本当になにをやっているのだろう、と思ってしまった。
「‥‥うるさい」
貴様のせいだ、と口にするのは意地が邪魔した。
だから目尻が熱いのは打った額がひりひりと痛むせいにした。
13.君をいじめることが楽しかったはずなのに
「‥ガユス‥」
「っ、なん‥だ、よっ‥!」
「そ、そんなにも泣くと、だ」
「‥っふ、」
「その、‥だな」
「‥な、にっ‥」
「瞳が溶けてしまうかもしれぬ‥」
「‥‥おまえ、やっぱり、馬鹿ッ、だ‥な」
14.誰にも君は渡さない
「堕ちたものだな」
「ああ、そうだな」
空は飛べても水には浮けない てめえがな
15.僕がどんなヒトになっても君は傍にいる気がする
玄関を潜り戸を開けて事務所の応接室へと身を滑らせれば、相棒の男が日向で呑気に寝こけていた。
目に入ったその平和な光景にギギナは顔を顰めずにはいられない。
自分達が生きる日常では考えられない、窓際での非常識さに。
足音は愚か、布擦れ一つ立てずに歩みを進め、間抜けな寝顔を覗き込む。
その面に違和感を感じたのは、寝相が悪いのか、知覚眼鏡が鼻の下にずり落ちていたからだ。
そのうち涎でも垂らしそうなその寝顔には苦笑するしかない。
暫しそれを眺めた後、ズレた眼鏡を定位置に戻すか外してやるかを暫し悩んで後者を選ぶ。
かたん、と机とフレームがぶつかる高い音で、昔の自分にはありえないその行動にまた苦笑する。
今の己が過去とは明らかに変化している自覚はある。
己を含めた周囲が変化したのだ。
ただ変わらないのはそこには常にこの男がいた事実。
目まぐるしく変わる中、この男だけは変わらないままで自分の傍にいる。
隣、ではなく傍に。
今も昔も、生者も死者も、変わらずこの男と共存している。
闘争を求めて止まないこの身体が、いつか灰燼に帰して、大地を疾る風に乗り、何処へと吹き抜け跡形も残らなくても、この男は記憶の中で永劫私と寄り添い生きるのだと思うと、自然と口角が吊り上った。
「‥‥私とおまえは、本当に―――」
言葉の最後は吹き込む風が攫っていった。
「‥‥い‥ッ!」
苦鳴に篭った意味を自分に良いように捻じ曲げているのはわかっていた。
「ギギナッ!」
わかっていても、吐かれた音が己の名である以上は止まれなかった。
例えそれが拒絶でしかない絶叫でも、だ。
「ア、ぐ!」
細い首。筋ばったその根元に、誘われるままに歯を立てれば生暖かい血が流れる。
傷口に舌を這わせて舐め上げれば、細い死体が腕の中で慄いた。
常から赤い口唇を更に彩る朱を認めた蒼い瞳がぐらりと揺らぐ。
逃げようとした肩が背後を望むが、壁と布が擦れる音がしただけ。
二人の距離は変わらなかった。
comment:もう君以外の色には染まれない
12.君がいなくなった朝は僕はただ呆然として
一昨夜よりも狭くなった、昨夜続きの寝台の上。
半覚醒のまどろみの中で腕を彷徨わせるが、しかし白磁のそれは虚しく空を切るばかり。
求めた温もりを掴むことは無かった。
「‥‥」
ぱちり、と目だけは開いている。
しかし思考は纏まらず、短針が刻む規則的な時間だけが一秒一秒積もってゆく。
「、ガユスッ!?」
ただ呆然とするしかない時間に終わりを告げて、既に冷え切っていた寝台から飛び降り、寝室から外へと繋がる扉へと一足飛び。取っ手を手に掛け飛び出そうとしたが、急いた身体は特急く身体と連携が取れず、目算誤り閉じたままの扉へ身体を打ちつけた。
思わずその場に屈み込む。
「‥‥なにやってんの?」
己の力では開けなかった扉の向こう、不思議そうな目で私を見下ろす男。
その手に湯気を立てる陶杯が二つあるのを確認した途端、言われた通り素直に、本当になにをやっているのだろう、と思ってしまった。
「‥‥うるさい」
貴様のせいだ、と口にするのは意地が邪魔した。
だから目尻が熱いのは打った額がひりひりと痛むせいにした。
comment:ギギはガユに関してはゾッコンヘタレが似合うと思う。
13.君をいじめることが楽しかったはずなのに
「‥ガユス‥」
「っ、なん‥だ、よっ‥!」
「そ、そんなにも泣くと、だ」
「‥っふ、」
「その、‥だな」
「‥な、にっ‥」
「瞳が溶けてしまうかもしれぬ‥」
「‥‥おまえ、やっぱり、馬鹿ッ、だ‥な」
comment:決して最中じゃありません(言うと怪しいよ)
14.誰にも君は渡さない
「堕ちたものだな」
「ああ、そうだな」
空は飛べても水には浮けない てめえがな
comment:そして二度と引き上がらない沼底へ
15.僕がどんなヒトになっても君は傍にいる気がする
玄関を潜り戸を開けて事務所の応接室へと身を滑らせれば、相棒の男が日向で呑気に寝こけていた。
目に入ったその平和な光景にギギナは顔を顰めずにはいられない。
自分達が生きる日常では考えられない、窓際での非常識さに。
足音は愚か、布擦れ一つ立てずに歩みを進め、間抜けな寝顔を覗き込む。
その面に違和感を感じたのは、寝相が悪いのか、知覚眼鏡が鼻の下にずり落ちていたからだ。
そのうち涎でも垂らしそうなその寝顔には苦笑するしかない。
暫しそれを眺めた後、ズレた眼鏡を定位置に戻すか外してやるかを暫し悩んで後者を選ぶ。
かたん、と机とフレームがぶつかる高い音で、昔の自分にはありえないその行動にまた苦笑する。
今の己が過去とは明らかに変化している自覚はある。
己を含めた周囲が変化したのだ。
ただ変わらないのはそこには常にこの男がいた事実。
目まぐるしく変わる中、この男だけは変わらないままで自分の傍にいる。
隣、ではなく傍に。
今も昔も、生者も死者も、変わらずこの男と共存している。
闘争を求めて止まないこの身体が、いつか灰燼に帰して、大地を疾る風に乗り、何処へと吹き抜け跡形も残らなくても、この男は記憶の中で永劫私と寄り添い生きるのだと思うと、自然と口角が吊り上った。
「‥‥私とおまえは、本当に―――」
言葉の最後は吹き込む風が攫っていった。
comment:ギギナが死んだらガユスは思い出を抱えて生き続けるんだろうなと思った
(write 06.9.6)
6.君が笑い声をたてるけど僕は少し面白くなかった
7.僕と君との出会いは奇跡だった
8.僕という存在を君は認めてくれる
9.僕の時間はいつの間にか君と止まっていた
10.君という小鳥はずっと僕の腕の中
7.僕と君との出会いは奇跡だった
8.僕という存在を君は認めてくれる
9.僕の時間はいつの間にか君と止まっていた
10.君という小鳥はずっと僕の腕の中
36.君は笑って、僕は俯いて
37.僕と君は違いすぎだよ
38.君は離れて行かないでね
39.君には君の世界があって
40.僕は君を守る盾となって
37.僕と君は違いすぎだよ
38.君は離れて行かないでね
39.君には君の世界があって
40.僕は君を守る盾となって
41.悲しいなら僕の腕の中で眠ればいいと君に囁く
42.雪のように穢れの無い君は僕の憧れで
43.君の声は透き通るような綺麗さで
44.恐れたことは君がいなくなること
45.振りかざした剣の切っ先を君に向けた
42.雪のように穢れの無い君は僕の憧れで
43.君の声は透き通るような綺麗さで
44.恐れたことは君がいなくなること
45.振りかざした剣の切っ先を君に向けた
46.例え僕がどうなろうとも君が無事ならそれでいい
47.怒り狂う僕に君は優しく囁く
48.笑わないで僕の話を聞いていて
49.君を置いて行ったりしないよ
50.君を好きになってどれくらいたったのだろうか
47.怒り狂う僕に君は優しく囁く
48.笑わないで僕の話を聞いていて
49.君を置いて行ったりしないよ
50.君を好きになってどれくらいたったのだろうか